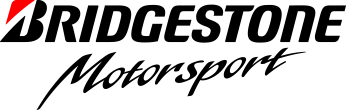| |||
ブリヂストンは技術と物作りへの情熱で | |||
モータースポーツジャーナリスト 今宮 純 |
モータースポーツジャーナリスト、F1解説者として雑誌、新聞、テレビなど多方面で活躍する今宮 純氏。F1初取材となる1973年のオランダGP以来、独自の視点でモータースポーツをわかりやすく、魅力的に報道解説し、モータースポーツファンのみならず多くの人々から支持されてきた。
長年にわたってF1を見つめ続けてきた同氏は、ブリヂストンのF1に至るまでの道程と、14年にわたるF1活動をどのように評価するのだろうか。
ブリヂストンがF1からの撤退を発表したあと、FIAやFOTA(F1に参戦するチームの団体)からブリヂストンに対して「何とかしてF1に残ってほしい」という声明が出されました。メディアを通じて報道されていたので、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、感慨深いものがありました。
長年F1を取材してきていますが、「お願いですから考え直してください」だなんてお願いが日本の企業に対してなされたことは公式・非公式を問わず、一度もなかったからです。今後もきっとないのではないかと思います。
ブリヂストンとしてF1にひとつの区切りを付けるという決定になったことは仕方がないにしても、このことはぜひ多くの方に知っておいていただきたい。世界中で何億人もの人が観戦する世界的なイベントであると同時に、ヨーロッパ発祥の「文化」としての側面、最先端技術のショーケースとしての側面を持つF1にとって、ブリヂストンは欠かすことのできない、唯一無二の存在になっていたのです。
もちろん、最初からそうだったわけではありません。
1963年に鈴鹿サーキットの誕生とともにモータースポーツ活動を開始し、日本国内のレースで数々の勝利をおさめ、1977年にはその技術を惜しげもなく注ぎ込んだカートタイヤをリリース。世界中の「F1ドライバーの卵」たちにブリヂストンの存在を強烈に印象づけ、世界進出への一歩を踏み出したまではよかったものの、初めて世界でのビッグレースとなったヨーロッパF2の2年目、ミシュランにたたきのめされてしまいます。
勝負に負けたということ以上にブリヂストンにとって屈辱的だったのはスポンサーシップなんて完全に無視して、シーズン途中に「こっちのタイヤのほうが速いから、お前のところのはもう使わない」とやられてしまったこと。
タイヤはレースの中では弱い立場に置かれていて、「タイヤは誰がつくっても同じだから、いいものができたら使ってやってもいいよ」という当時のレース界におけるタイヤの位置づけというものを物語るようなできごとでもありました。
そこでブリヂストンがやったのが、翌1983年に、日本からのタイヤをプールし、サービスチームとともに各サーキットへと送り届けるための前線基地を現地につくるということ。
それまでは、日本から運んだタイヤはチームのトレーラーに便乗させてもらってサーキットに運搬し、エンジニアの浜島さんがフィッターも兼ねる......といった体制だったと記憶していますが、ヨーロッパ流の「分業制」に改めることで当時最先端の技術だったラジアルタイヤの開発に専念できるようにしたのです。
現地にベースをつくり、現地のスタッフを雇用してヨーロッパにしっかりと根を降ろし、チームと対等な立場で話ができるようにしたことが非常に大きかったと思いますね。本当の意味で、きちんと海外に進出していったということです。
その後、1985年に欧州F3000 (F2の後継カテゴリー)で12戦9勝を挙げてチャンピオンタイヤとなり、DTM、ITCを経て徐々に自動車メーカーやレーシングチームとの関係の中で存在感を強めながらも、水面下でコツコツとF1への準備を進め、ついにF1へと参戦することになるわけです。
世界中に衝撃を与え、ブリヂストンの存在を特別なものにしたのは1997年のハンガリーGPでしょう。
アロウズのデイモン・ヒルがトップを快走、あわや優勝か、と思わせたあのレースです。当時明らかにトップを走るようなポテンシャルを持っていなかったあのチームがトップを走ったのは、ブリヂストンにしかつくれないタイヤのおかげだということが誰の目にも明らかだったからです。
この活躍がマクラーレンの目にとまり、翌年の契約に結びついたのはもちろん、グルーブド(溝付き)タイヤとなって、「仕切り直し」になったにもかかわらず、グッドイヤーに競り勝ったことで、ブリヂストンの地位は揺るぎないものになったのです。
この頃になると、もう誰も「タイヤは誰がつくっても同じだから、いいものができたら使ってやってもいいよ」とは言いません。当時マクラーレンのチーフデザイナーだったエイドリアン・ニューエイが、浜島さんとかなり激しくやりとりをしながら開発を行ったように、マシンはタイヤと歩調を合わせて設計されるものになりましたし、タイヤにあわせてドライビングを組み立てないドライバーもいません。
これは、自らの積み重ねてきた技術に対する自信と、製品に対するプライドのあるブリヂストンだからこそ実現しえたことでしょう。
その後迎えたワンメイク時代で全チームへの公平なタイヤ供給と、完璧なロジスティックを行い、もはやブリヂストンはF1にとって欠かすことのできない存在になっていったのです。
F1を撤退したブリヂストンが、次にどんな活動をするのか......それは楽しみにしていますが、モータースポーツは新技術の開発やエンジニアの育成などの面でタイヤメーカーのものづくりを象徴する活動であり、切っても切り離せないものである、と私は考えています。
「F1に替わるもの」というのは、きっと存在しないのではないかと思いますね。
あと何年かすれば世界のタイヤメーカーを取り巻く環境も大きく変わっていることでしょうし、1990年代後半から2000年代はじめの、「F1激動の時代」の中で確かな存在感を持っていたブリヂストンの時代というものが、歴史的に語られるときが来るでしょう。
そこで、F1の長い歴史の中におけるブリヂストンの果たした役割がいかに大きなものだったのか、有意義なものだったのかを、客観的に眺めるときが来たなら、ぜひもう一度、世界最高峰の舞台で戦うということを検討してみてもらいたいものです。

技術競争ではコンペティターとの対決に勝ち、2度のワンメイク期間では公平なサービスを行ってきたブリヂストンはF1界からの厚い信頼を獲得。欧州発祥の「文化」であり、最先端技術のショーケースとしての側面を持つF1で唯一無二の存在となっていた。

ブリヂストンは1981年から参戦を開始した欧州F2で、参戦初年度にしてチャンピオンタイヤとなる。翌年はミシュランに、完膚無きまで叩きのめされてしまう屈辱も味わうが、欧州に根を下ろし、地道な技術開発を行うことで1985年に再び王座に返り咲いた。

観るものをあっと言わせた1997年のハンガリーGP。開幕戦の時点では戦闘力不足に悩まされていたアロウズのD.ヒル選手が、M.シューマッハ選手を抑えてトップを快走。タイヤでレースが変わるということをF1界に強く印象づけた。

1998年、名門マクラーレンは、タイヤをブリヂストンにスイッチ。エイドリアン・ニューウェイのデザインしたマシンとブリヂストンのタイヤは抜群のマッチングを見せ、マクラーレンは見事ダブルタイトルを獲得することができた。