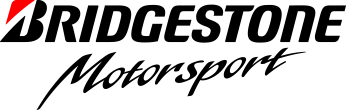マクラーレンとパートナーシップを結んだことの効果は、開幕戦から早くも表れる。
ブリヂストンタイヤを装着したマクラーレンの2台が、他チームのすべてのクルマを周回遅れにして、ぶっちぎりで初優勝。
その勢いは衰えることなく、ブリヂストンにとって2度目の凱旋レースとなった第16戦の日本GPで、初タイトルまで獲得するのである。
トップチームの底力を痛感
97年12月1日。オフシーズンテストの解禁日であり、マクラーレンとのコラボレーションが始まった日でもある。そこから始まるオフシーズンテストを通じて、浜島はトップチームがトップチームたる所以を痛感する。
「テストのために用意したタイヤが、あっという間になくなってしまうんですよ! なぜかというと、とにかくテストの実働時間が長いんです」
例えばエンジンにトラブルが発生したとする。それまでのブリヂストンのパートナーは、いちいちエンジンをバラし、それからまた組んで......となるため、およそ3時間は走ることがない。「その間は休憩していました」(浜島)となるわけだ。ところがマクラーレンでは、休んでいる暇はない。エンジンユニットごと交換するので、30分もすれば再び走り出せてしまう。その結果、走行時間も距離も当然長くなり、タイヤが足りなくなってしまったわけだ。
「これがトップチームの開発力か......」
それは、参戦2年目にしてブリヂストンが知った、F1トップチームの底力であった。

熱くなった、空力の天才との議論
2010年、F1を席巻したレッドブル旋風。そのマシンをデザインしたエイドリアン・ニューウェイが98年当時在籍していたのが、マクラーレンだ。浜島は当時、そのニューウェイとかなり激しい議論を展開したのだという。しかし、それは当然のことではあった。グッドイヤーのタイヤをベースに98年用マシンをデザインしていたニューウェイにとってみれば、チームがブリヂストンと契約したことは、ある意味、降って沸いたような話だったのかもしれない。
「クルマは昨年(97年)のタイヤサイズをもとにして設計している。四の五の言わずに、そのサイズのタイヤを持って来るんだ!」とニューウェイ。だが、浜島は従わなかった。
「そのサイズでは、すぐにアンダーステアになってしまう。それがわかっているタイヤは持っていけない!」と浜島。長年にわたってレーシングタイヤを開発し続けてきた者としての意地、そして自分たちが開発してきたタイヤに対する根拠と自信があった。
平行線が続いたその話し合いを終わらせるためには、実際に走らせ、速さを発揮するしかなかった。すると、ライバルたちがアンダーステアで苦しんでいる中、マクラーレンは見事なパフォーマンスを発揮。結局、ニューウェイもブリヂストンの主張を受け入れるしかなかった。

初PP、そして念願の初優勝!
オフシーズンテストで走り始めたときから、マクラーレンとブリヂストンは素晴らしいパフォーマンスを発揮していた。とはいえそれはあくまでテストでの話。各チームとも、本当の姿がそこで見えているわけではない。だから浜島も、マクラーレンが速いだろうということはわかっていても、「なんとか勝たせてもらえればいいのだが......」と考えていた。
98年開幕戦オーストラリアGP。マクラーレンの速さは、予選から際立っていた。そのスピードはレースになって衰えるどころか、ますます冴え渡っていく。
「モニターを見ていてもわかるんですよ、速さの違いが。マクラーレンは最終コーナーを"ヒュンッ!"と出てくる。でもグッドイヤー勢は違うんです。速いのは1周だけで、次の周回にはアクセルを戻している。それを見て、エイドリアンとケンカしてでもタイヤのサイズを守ってよかった、と。本当にそう思いましたね」
結果はマクラーレンの1-2フィニッシュ。しかも、3位以下全車を周回遅れにするほどの、ぶっちぎりの勝利であった。
鮮やかにすぎる勝利を飾ったブリヂストン&マクラーレンは続く第2戦ブラジルGPも制する。しかし、第3戦アルゼンチンGPで、早くもグッドイヤーが動いた。グッドイヤーもブリヂストン同様、フロントタイヤのサイズを変更したものを投入し、フェラーリのミハエル・シューマッハが反撃を開始したのである。
これには浜島も、「アルゼンチンにサイズを変えたフロントタイヤを持ってきたのは、驚きましたね。グッドイヤーが、そんな臨機応変な対応をするとは! という。きっと冬のテストのときからミハエルにあたりに言われていたんだとは思います。でも、それからわずかな時間で開発してくるのはさすが。彼らの底力を感じましたよ」と感嘆する。
勝ち逃げは許すな......そんなスローガンのもと、一丸となって戦っていたブリヂストン陣営の気持ちが、よりいっそう引き締まっていった。


大波乱だったベルギーGP
「あのレースのことはよく覚えています」と語るのは、98年からF1の、しかもマクラーレンの担当となった菅沼寿夫だ。
そのレースというのは、第13戦ベルギーGPのこと。"スパ・ウェザー"と呼ばれるほどに、雨のレースが名物となっているベルギーGP。このときもスタート時はスターティンググリッド付近は濡れているが、雨は降っていないという状況だった。そんな状況下でマクラーレンのエンジニアと、ポールポジションを獲得したハッキネンの間で、次のような会話が交わされたという。
「インターミディエイトとウエット、どっちにする?」とエンジニア。するとハッキネンは、「ブリヂストンに聞け」と答えたというのだ。この問いかけは、当然のように菅沼に回ってきた。この時点でスパ-フランコルシャンのすべての路面を見ていたわけではなかった菅沼は、「ほかに合わせよう」と答える。そして、新たなコンパウンドが投入されたインターミディエイトタイヤを採用するのだ。ところが......スタート直後の1コーナーでハッキネンはスピン。いきなりのクラッシュでレースを終えることとなってしまう。
「あれはショックでした。本当にいまでも忘れられない。失敗したことは、よく覚えていますね。そして、やっぱり雨のレースは嫌ですねぇ(苦笑)」
このレース、その後も波乱が続く。圧倒的な速さでレースをリードしていたシューマッハが、クルサードに激突。「クルサードが突然進路を変えたためだ」と主張するシューマッハが、マクラーレンのガレージに怒鳴り込んできた。そのシーンを見ていた菅沼は、「まさに鬼の形相でしたよ。クルサードだって、別にわざとやったわけじゃないのにね」と振り返る。菅沼にとっては、さまざまな意味で記憶に残る、ベルギーGPだった。


戦ってつかんだ、初めてのタイトル
マクラーレンを軸としながら、グッドイヤーに是が非でも勝つ、という気持ちのこもったレースを続けるブリヂストン。もちろん、グッドイヤーも有終の美を飾るべく、ミハエル・シューマッハとともに激しい追撃を続けてくる。最終戦日本GPを前にポイントリーダー、マクラーレンのミカ・ハッキネンとシューマッハのポイント差はわずかに4ポイント。鈴鹿でのレース結果ですべてが決まる。
「意気込みは前年とはまったく違いましたね」と浜島。その緊張感はブリヂストンのスタッフ全員が感じていたものだったのではなかったか。浜島は続ける。「スタート前に当時の海崎社長に言われたんですよ。"浜ちゃん、タイトルを取っても取らなくても、使ったオカネは同じだから"って。タイトルを取れば価値あるオカネ、取れなければ捨てたオカネ......そういう意味だと思います。もちろん、励ましていただいた、ということですけどね」
そんな大事なレースで、ブリヂストン/マクラーレン陣営は、予選に失敗してポールポジションを取り損ねてしまう。「大丈夫、ちゃんとついていければ......」と、浜島は自分を励ましながら様子を見守っていたという。そして迎えた決勝のスターティンググリッドでシューマッハがエンスト。一気に最後尾にまでポジションを落としてしまう。これでハッキネンのタイトル獲得は確実かと思われたが、シューマッハがあっという間にトップ10までポジションを挽回する。「なんだこれは......」と浜島たち、ブリヂストンのエンジニアもいろめき立つが、シューマッハの追撃はそこまで。最後はシューマッハの右リアタイヤがバーストし、ストップしてしまうのだ。止まった場所は、ブリヂストン応援団席の目の前だったという。
参戦2年目でのタイトル獲得、そしてグッドイヤーの勝ち逃げを許さなかったこと。
「出来過ぎです」という浜島。しかし、これは決して偶然などではないだろう。この年から採用された溝付きタイヤの研究と開発、その結果でき上がったものに対する自信を裏づけとするチームの説得(例えば、前述のニューウェイとのせめぎあいなど)など、ブリヂストンは、2年目でタイトルを獲得するだけの努力を、すでに十分以上に重ねていたのだから。