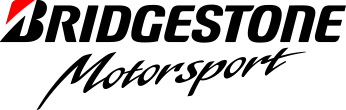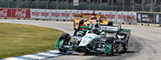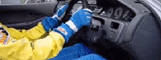ついにF1の舞台に立ったブリヂストン。待っていたのは、アメリカの巨人グッドイヤーとのコンペティションだった。
トップチームを陣営に抱えるグッドイヤーに対し、ブリヂストンは卓越したアイデアと
強固なファイティングスピリットを持って、立ち向かっていく。
コンペティションは前年から始まっていた
強豪グッドイヤーとの戦いは、参戦前年の96年からすでに始まっていた。それはブリヂストンのエンジニアが、モータースポーツ推進室長・安川ひろしに託した、レースウィークに使えるタイヤのセット数に関するレギュレーションの改定に顕著だ。
「それまでF1にタイヤを供給していたのは、グッドイヤーだけ。ワンメイクゆえか、決勝は7セットのタイヤで戦われていたんです。しかしウチのエンジニアが"それではもたない。8セットにしてほしい"と。そのレギュレーション変更を97年開幕戦に間に合わせるためのFIAとの交渉は、ずいぶんと骨が折れました」
結果、97年は決勝で8セットのタイヤを使用することが、レギュレーションで認められる。

本当に開幕戦に間に合うのか?
97年開幕戦、オーストラリア。レースを戦うためにメルボルンの街に入った浜島は気が気ではなかった。「ちゃんとものが揃うのか......」。初めてゆえの不安である。機材はほとんどが新たに購入したものばかりで、しかも日本ではなくイギリスからやってくる。タイヤフィッターもイギリスから。エンジニアはイギリスと日本から。そして肝心のタイヤは日本から。
さらに浜島には、もうひとつの心配があった。コースだ。ブリヂストンは、F1参戦を決めてからヨーロッパの多くのパーマネントサーキットでテストを行っていた。しかし、開幕戦オーストラリアGPの舞台は市街地コース。走ったことがない。大恥をかかないだろうか......浜島の胸には、そんな心配が去来していた。
走ったことがないから、どんなタイヤを持っていけばいいのか......「当時はオーストラリアのツーリングカーにタイヤを供給していたので、それを参考にはしましたが......」と言うのは、全日本F3000のタイヤ開発から96年にF1部門に移り、開発に従事してきたコンパウンド配合技術者の崎山淳だ。
「準備は万端に済ませてきたのだから、普通なら"いよいよ始まる。ワクワクする"と思ってもいいはず。これまでにやってきたレースなら、そうでした。でもあのときは"本当に大丈夫か"という不安と恐怖しかありませんでした」
1回目のフリー走行は何事もなくが終わり、ようやくホッとしたという浜島。同時に、戦えるという手ごたえを感じた浜島は、ブリヂストンのタイヤ特性を活かした戦略を、チームに伝えることを思いつく。しかし、果たしてその提言は受け入れてもらえるのか......それが決勝に向けての新たな心配事だった。


タイヤから戦略を考える
それは、プロストの苦虫を噛み潰したような顔に現れていた。
浜島は、決勝のレース戦略について、チームオーナーであり、かつてのワールドチャンピオンであるアラン・プロストに、ある提言を行っていたのだ。
「我々のタイヤは磨耗がよい。ピットストップを1回減らしましょう」
初めてのF1予選。ブリヂストン陣営の最上位はプロストのオリビエ・パニスで9番手。ポールポジションのジャック・ビルヌーブ(ウィリアムズ)から3.473秒遅れという結果だった。浜島の提言の背景には「予想以上に(結果が)よかった」という手ごたえがあったのだ。
しかしプロストにとっても、このレースはデビュー戦。ピットストップを減らすということは、クルマが重くなり、ブレーキにも厳しくなる......本音としてはやりたくない......プロストの表情には、そんな思いが見え隠れしていた。
だが、最終的には浜島の提言が受け入れられた。そして結果は......デビューレースで見事に5位入賞。それはプロストとブリヂストンの信頼関係が、ひとつ先の段階に進んだ瞬間であった。

ライバルを本気にさせた
開幕戦で初入賞を果たしたブリヂストンは、続く第2戦ブラジルGPではさらなる飛躍を果たす。予選で5番手につけたパニスが、3位でチェッカー。2戦目にして早くも表彰台の一角に立つのである。これには安川も、浜島も驚いた。浜島は、「"あれっ? 表彰台?"って半信半疑の気持ちで見ていました。うれしいというより、出来過ぎだよ、という思いのほうが強かったですね」と述懐する。
シーズン序盤が荒れたレース展開になることは、よく見られることではある。開幕戦が完走10台のサバイバルレースであったことにも、それは現れている。とはいえ、これもレースでよく言われることであるが、重要なのは「そのとき、どこにいたか」ということ。いるべきときに、いるべき場所にいたからこそ、ブリヂストンとプロストは、初レースで初入賞、さらに2戦目にしての表彰台を獲得したわけだ。
するとライバル陣営に変化が現れた。浜島は、当時のことを次のように振り返る。
「わかりましたよ、彼らが焦っているのは。だって、ウチが契約しているのは中堅以下のチーム。それが予想を超える結果を出しているわけですから。きっとトップチームから言われたんじゃないですか、いろいろと。だから予選でポジションを取るために柔らかいタイヤを入れて、結果レースでブロウさせたりといったことが起こった......。我々としてはしてやったり! ですよね」
そんなライバルを見て、ブリヂストンは確信するのだ。「自分たちは間違っていなかった」ということを。
使い始めのグリップ性能と使い終わりのそれにおける「落差」の少ないタイヤ......それこそが、レーシングタイヤの王道なのだという哲学。その哲学に沿って、自分たちが信じて歩んできた道を、そのまま愚直に突き詰めていけばいいということを、参戦初年度にしてブリヂストンは確信するのである。


初優勝が見えた日
1997年8月10日。ハンガリーの首都ブダペストの郊外にある、ハンガロリンクのピットウォールに、レースの行方を固唾を呑んで見守るふたりの日本人の姿があった。ヤマハの木村隆昭プロジェクトリーター(当時)とブリヂストンの浜島である。
目の前では夢に見たシーンが展開されていた。自分たちが開発したエンジンとタイヤを搭載したF1マシンが、ラップリーダーとして、ハンガロリンクを周回している。優勝まで、あとわずかの走行を残すのみ。しかしラスト2周、思いがけないドラマが待っていた。勝利を目の前にしてクルージング・モードに入っていたデーモン・ヒルのペースがさらに落ちていくのだ。油圧系のトラブルが原因だった。ギアが2~3速にしか入らず、ペースはどんどん落ちていく。背後には、みるみるうちに2位を走行していたウィリアムズのジャック・ビルヌーブが迫る。そしてレース残りわずか4分の3周というところで、ついに逆転。
ヤマハの、そしてブリヂストンの初優勝の夢は泡と消えた。
「木村さんは悔しかったと思います。(ヤマハにとっては)唯一のトップ走行だったし......僕らは、ハンガロリンクで勝てなかったことで、かえって気を引き締めることにもなった。しかしヤマハの人たちにとっては......本当に残念なレースでしたね」。
悔しい思いはブリヂストンも同じだった。唯一違うのは、ブリヂストンがF1にやってきたばかりなのに対し、ヤマハは97年の最終戦をもってF1から撤退することになってしまったことだ。
シーズン序盤、ライバルを焦らせるほどのパフォーマンスを見せていたブリヂストン。しかし第7戦のカナダGPで陣営のエースドライバーともいえるパニスがクラッシュ。それがきっかけとなったかのように、次第に当初の勢いが失われていく。
特に第9戦のシルバーストンや第10戦のホッケンハイム、第13戦のモンツァといった高速で、エンジンのパフォーマンスがものをいうコースでは苦戦を強いられた。
「パワー勝負のコースでは全然歯が立たない。タイヤだけではどうにもならないレースがあるということを思い知らされて......ショックでした」
だからこそ第11戦のハンガリーGPの戦いは印象的なものだった。戦いの舞台となるハンガロリンクはモナコと並ぶ低速コース。つまり、エンジンのパワーが絶対的な優位とはならないコースだ。さらにハンガリーGPは毎年、真夏の開催となり、暑さとの戦いも強いられる。その状況を踏まえ、ブリヂストンは高温への対策も施したソフトタイヤを、絶対的な自信とともに持ち込んでいたのだ。
そして、そのタイヤのパフォーマンスを信じたアロウズ・オーナー、トム・ウォーキンショーとデイモン・ヒルが演じた渾身のレース。それが、この年のハンガリーGPである。それは同時に、"パワーが絶対的な優位とならないコースならば、タイヤの性能差で勝負を変える事ができる"ことをブリヂストンが証明したレースでもあった。
「タイヤ設計者冥利につきるレース」
浜島は、97年のハンガリーGPをそう振り返った。
そして、このレースは後にライバルとなる、あるタイヤエンジニアのハートにも火をつけた。2001年からF1で戦うことになるミシュラン(当時)のパスカル・バセロンは後にこう語っている。
「開幕戦の時点ではトップを走る力を持っていなかったアロウズが、ミハエル・シューマッハをオーバーテイクしたとき、私の在籍していたミシュランを含めた誰もが確信したはずです。"タイヤでレースを変えられる"と」
当時、クルマのパフォーマンスにおける重要度はエアロダイナミクスにあった。しかし、ブリヂストンの参戦以降、そしてタイヤの開発競争が始まるころには、タイヤ開発は、エアロダイナミクスと同じくらいに重要な要素になっていくのである。





トップチームが欲しい
「どうしてウチにタイヤを出さない?」
ある日、安川はメルセデスのノルベルト・ハウにそう語りかけられた。ブリヂストンとメルセデスは、すでにドイツ・ツーリングカー選手権(DTM)においてパートナー関係にあった。そのパフォーマンスを理解するハウだからこそ、安川にそう声をかけたのだ。
「とはいえウチが契約するのはメルセデスではなく、マクラーレンということになりますからね」
安川は、そう答えるしかなかった。ところが、だ。97年シーズンが進むうちに、マクラーレンからのアプローチを待つだけではいけない状況が生まれてくる。
モータースポーツ推進室長の安川とともに、マネージメント部門を担当していた堀尾は当時をこう振り返る。
「発表前にバーニー(・エクレストン)から安川に連絡があったんですよ。『グッドイヤーが撤退を検討している』と。ブリヂストンのスタッフはみんな目の色を変えましたね。『まずい。このままでは勝ち逃げされる』と」
すると、安川もチームとの交渉の方法を変えざるを得なくなる。
「グッドイヤーが撤退するというのが本当のことならば、勝ち逃げを許すわけには行かない。そのためには、勝てるチームを陣営に迎え入れなければなりません。ということで会社に進言し、マクラーレンとの契約交渉を開始させるのです」
ここで気をつけなければならなかったのは、マクラーレンとグッドイヤーの間の契約だ。安川はマクラーレンに対し、「まずはグッドイヤーとの契約をクリアして欲しい。ウチとの契約を進めるのはそれから」と持ちかける。
結局、その後グッドイヤーが98年を持ってF1 から撤退することが関係者の知るところになる。グッドイヤーがその事実をなかなか公表しなかったために、マクラーレンとの契約、そしてその発表が遅れるというドタバタはあった。しかし、これでついにブリヂストン陣営に、"名門"と呼ばれるトップチームが加わるのである。


エンジニアとは違う視点で見たF1
イギリスでの事務所探しからスタッフの手配、トランスポーターなど数え切れないほどの備品の整備といった事務的な作業はもちろん、チームやFIAとの契約やメディアへの対応など、その課程において、数え切れないほど大勢の人とフェイス・トゥ・フェイスの付き合いをしてきた堀尾は、エンジニアとは異なる視点からF1を生きる人々の顔を見てきたようだ。
例えば、参戦初年度にパートナーシップを組んだ、かつてのワールドチャンピオン、ジャッキー・スチュワートについての印象を、次のように語る。
「プロ意識の高い方ですよね。実は、第一印象はそれほどいいものじゃなかったんですよ。"口の上手い人"というタイプ見えたんです。でも、そうじゃなかった。彼の話術は素晴らしいんです。お客さんを圧倒させる、話し方なんですよね。そして実際に仕事で組んでみると、こちらがお願いしたことにはきちんと対応してくれる。本当のプロですね」
チームの統率力という意味では、参戦2年目からパートナーとなったマクラーレンのレベルの高さに感心したという。「完璧主義者であるロン・デニスのDNAが隅々まで行き届いている」と言うのだ。
「マクラーレンは、スポンサーに対してすごく気を使っているのがわかるんです。その気遣いは、"プロ"だからこそ、ですよね。それにマクラーレンのピットとか、すごくきれいなイメージがありませんか?
スペシャルなんですよね。その意識は、ファクトリーに行っても一緒。そういうところまで含めて、"F1はショービジネスでもあるんだ"という意識が徹底しているんだと思います」
ジャッキー・スチュワートにロン・デニス......F1のレジェンドともいえる元ドライバーにチームオーナー......そんな大物たちと至近距離で仕事をしてきた堀尾。参戦初年度97年の大きなトピックスであるハンガリーGPについて、次のようなエピソードを披露してくれた。
「レースが終わり、表彰台に上る3人がキャップをかぶりますよね。当時は、タイヤメーカーの担当者が、直接ドライバーにそのキャップを手渡していたんです。それでハンガロリンクって、モーターホームと表彰台が離れていたんですね。レースが終わってから持って行ったんじゃ遅いっていうので、ファイナルラップの前に、私が「1stキャップ」を手に走っていったんです。ところが、表彰台のところについたらグッドイヤーの人間が「No,no!」って言うんですよ。それからレース結果を確認したら2位になっていて......残念でしたよね」
エンジニアとは違う視点と関わり方でF1を戦ってきた堀尾。それもまたブリヂストンの貴重な財産として、これからの活動に活かされていくはずだ。