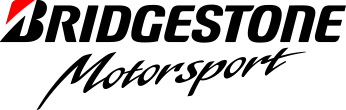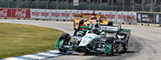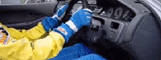まさかの苦戦である。前年の圧倒的な強さから一転、この年はわずか1勝に終わる。
その1勝とは、F1史上かつてない展開を見せたレース。
6台のブリヂストン装着車のみが出走し、フェラーリがワンツーフィニッシュを決めた、あのアメリカGPである。
緊張感いっぱいだった開幕戦
2005年シーズン開幕戦メルボルン。ブリヂストンも、ミシュランも、例年とは異なる緊張感を感じていた。
タイヤは持つのか......。
彼らが感じていた緊張感の最大の理由は、この年、大きく変わったレギュレーションにあった。予選と決勝を、1スペックのタイヤで、しかもタイヤを交換せずに走りきらなければならなくなったのだ。
「そのため2004年とはまったく違うタイヤにしなければならなかった」
そう浜島は言う。それほど大きな変化であり、新しいタイヤを開発しなければならなかったのだ。しかし、ここで大きな問題が出てくる。開発テストの遅れだ。
2004年シーズンといえば、「全戦全勝」の勢いで、シーズン終盤まで開発を進めていたシーズン。ライバルが早々に開発を翌2005年にシフトしていく中、ブリヂストンとフェラーリはギリギリまで2004年を戦うためのテストに費やしていた。フェラーリが2005年用タイヤのテストに本腰を入れ始めたのは、2004年シーズンが終わり、オフシーズンテストが始まってからであった。
「ミハエルが言って来るんですよ。"パフォーマンスはいいけど、(予選から決勝まで)持つのか?"と」
しかし当時、浜島はこの問いかけにその場で答える事ができなかったという。なぜなら、テストしたタイヤをもう一度東京のテクニカルセンターに持ち帰り、ケースの耐久性テストをやり直す必要があったからだ。そこまでしなければ、安全性と耐久性を確認することができない。そして実際、東京で耐久性テストをやり直すと、「400kmの走行には持ちません」という結果が出たこともあったそうだ。
2005年に向けたテストの立ち上がりの遅れは、そのまま開発の遅れにつながってしまった。そして、"これだ!"という自信を持てないまま迎えた開幕戦にブリヂストンが用意したのは、耐久性と安全性を優先させたタイヤ。つまり、どうしても戦闘力という点では我慢をしなくてはならないタイヤということになる。
「仕方ありませんでした。だって、そのタイヤじゃなければ、タイヤが壊れてしまうことはわかっていましたから......非常に苦しく、そして緊張感のある開幕戦でした」(浜島)
結局ブリヂストンの2005年開幕戦の結果は、フェラーリのルーベンス・バリチェロが2位。そのほか上位陣にはミシュラン勢が名を連ね、シューマッハは42周目に他車と接触、リタイアに終わった。



前代未聞のアメリカGP
「事件だったよね」と、この年のアメリカGPを振り返るのは、モータースポーツ推進室長の安川だ。
発端はアメリカGP初日、金曜日のフリー走行で起こったクラッシュであった。ミシュランを履くトヨタのラルフ・シューマッハが、インディアナポリスの特徴的なオーバルコースを生かした最終コーナーでクラッシュ。原因は左リアタイヤが壊れ、パンクしたことだった。しかし、これは単なるパンクではなかった。ミシュランがさらに原因を調査すると、タイヤが荷重と速度に耐え切れずスタンディングウェーブを起し、タイヤのショルダー内部が切れて一気に空気が抜ける症状が出ていた。さらに悪いことに、その症状はほかのミシュラン装着車数台からも出ていたのだ。
この調査結果を受けながらも、予選に出走したミシュラン勢。しかし予選が終わるとミシュランが「予選で使ったタイヤは安全が保証できない」とし、FIAに対し、「バンクの手前にシケインを作り、速度が低下するようにしたい」と提案してくる。
FIAは当然この提案を一蹴し、「スピードを落として通過するか、ペナルティを覚悟して別のスペックを使うように」との判断を下す。
アメリカGPは、レースの開催を巡り混乱を極めた。バーニー・エクレストン自らが安川のもとを訪ねて、こうも話したという。
「"ヒロシ、君のところのタイヤを使うチームだけでも走らせてくれよ"と」。
もちろんそのつもりだった。F1を楽しむためにインディアナポリスに詰め掛けた大勢のファンのためにも、レースは開催されなければならない......。そう考えていた安川は、奔走する。「すぐに陣営のチームに説明して回りました。フェラーリは、すぐにOKしてくれましたよ」
果たしてレースは行われるのか、行われないのか。パドックは不穏な空気に包まれ、そして、あの奇妙な決勝レースのスタートのときを迎える。ダミーグリッドには全車がつき、いつものようにフォーメーションラップが始まる。ところが、周回を終えて本来ならスターティンググリッドに向かうべきクルマの大半......つまりはミシュラン装着車はピットロードへ。ミシュランは、この年のアメリカGPを戦わずして敗れたのだ。


安全性を優先することの正しさを証明
前代未聞のアメリカGP。ミシュランが戦わずしてその舞台を降りたあと、スターティンググリッドについたのはブリヂストンを装着する6台のみ。フェラーリ、ジョーダン、ミナルディである。ライバルが不在なのだから、安心してレースを見ていられると思ったら、そうではなかったと浜島も、菅沼も、口を揃える。
「だってタイヤが壊れないことが絶対的な使命になっていましたからね。もしタイヤが壊れたら、"ほら見ろ、ブリヂストンも壊れたじゃないか!"とミシュランが言ってくるのは明白でしたから。祈るような気持ちでレースを見ながら、担当エンジニアにはとにかく内圧のセンサーをチェックして、少しでも異常があったらすぐに知らせろ、と指示をしていました」(浜島)
「ここでウチが壊れたら、かっこ悪いよな、と。だから必死でしたよ!インディアナポリスは非常に高速になる部分と低速部分の合わさった特徴的なコースレイアウトをしています。特にオーバルの一部を使った部分というのは、タイヤの負担は大きくなるものなんですよ。ですから内圧が低くなりすぎないように、ずいぶん気を使いましたね」(菅沼)
そんな彼らの心配をよそに、コース上には興奮した観客からペットボトルが投げ込まれたりした。またシューマッハとバリチェロがバトルして魅せるシーンも。
「彼らにしてみれば、お客さんにレースらしいところを見せなきゃ、という思いだったんでしょう。それは理解できるけど、こちらとしては"(タイヤに大きな負荷がかかるような)余計なことをしないでくれ!"って感じでしたよ(笑)」(浜島)
結果的に、このアメリカGPが2005年唯一の勝利である。しかし、ある意味においてこの1勝は何ものにも代えがたい、価値ある勝利となった。なぜか......それは、ブリヂストンが掲げる"安全第一"という哲学の正しさが証明されたレースだからだ。
「普通、タイヤのケースの耐久性についてのテストは、現場ではやらないんです。しかし、この年はすべてのレースにテスターを持って行き、400km走ることができるタイヤであるかどうかを確認しながら戦っていました」(浜島)
安全性確保を第一に考える、その高い意識。「その意識を含め、我々の哲学は間違っていないと再認識しました」と、浜島は胸を張った。


ブリヂストンのエンジニアとして戦うということ
14年間のF1活動の中で、大勢のエンジニアがその戦いに身を投じてきた。2003年にはBARを、2004年にはザウバーを、そして2005年はF1テストのトラックエンジニアを務めた福武良一も、そんなエンジニアの一人だ。
「03年と04年は、担当チームが走行するすべてのテスト、レースに帯同し、チームのタイヤに関するすべての業務......走行タイヤの解析からタイヤテスト業務全般、レースサポートまで......を行いました。05年はブリヂストンがサポートするタイヤテストの準備を担当しました。テストメニューを作成し、そのためのタイヤを準備する、ということですね」
当時はレースとレースの合間に合同テストがあり、さらにフェラーリは毎週テストを行っていた。フェラーリのほぼすべてのテストに帯同していた福武は、「ロンドンに住まいがありながら、05年はイタリアに80泊以上していました」という。
多忙を極めるエンジニアは、さまざまな苦労に直面する。言葉についてはもちろん、福武が特に苦労したのは健康管理だという。
「テストの時は朝8時から夜中の12時くらいまでサーキットにいるのが普通なんです。ホテルに戻るギリギリまで仕事をしているせいか、ホテルに戻ってもなかなか気持ちが切り替わらない。リラックスするために、ついビールを......なんてことも。睡眠不足との戦いでしたね」
そして最大の苦労は、テストを行っているヨーロッパと、タイヤを設計・製造する日本の距離というか、危機感の温度差を、いかに縮めるかということだった。現場にいる者のできることとして、レポートの質の向上に努めるも「なかなか思うようにはいかなかった。特に苦戦の続いた2005年は悩みましたね」と福武。
また、こんなエピソードもある。チームの勝利に賭ける情熱を表すものとしてと語ってくれたのは、フェラーリとの共同開発プロジェクトを担当していた小松秀樹だ。
「2005年は、思うような成績が残せず、ひいてはコンパウンドの開発もうまく進んでいなかったんです。そのことに業を煮やしたのか、あるときフェラーリのエンジニア2人がわざわざ東京までやってきて、我々に発破をかけてすぐにイタリアに帰っていく、ということがあったんです。普段はテレビ会議だけなのに、わざわざお金と時間をかけて発破をかけにきた意味は重いですよね......。そんなことがあっただけに、ミシュランとのコンペティションが終わった2006年、フェラーリとの共同開発プロジェクト最後の会議を迎えたとき、そのエンジニアが"レベルの高いエンジニアと仕事ができて、とても楽しかった"と言ってくれたときは......感無量でした」
言葉も文化も違う環境で、休む間もなく続く戦いの日々。そこに身を投じてきたエンジニアたちの最大の目的は、自分たちの開発してきたタイヤのパフォーマンスの高さを証明すること......つまりレースに勝利することである。
その目的が達成できたとき、苦労は苦労ではなくなるのだ。