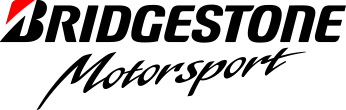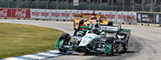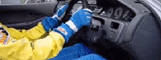ヨーロッパF2でタイヤ開発技術のレベルを高めたブリヂストン。
1990年代は、DTMやインディへとチャレンジの世界を広げ、新たな経験を重ねる。
そのすべてがF1へと通ずる技術と経験の蓄積となった。
1991年、
ドイツでF1に匹敵する人気を誇るDTMへ参戦
「AMG(メルセデス・ベンツのチューニング部門)のドミンゴス・ピアダーデ副社長(当時)の息子さんがカートのレースをやっていて、アルトン・セナとも仲が良かったのです。セナはブリヂストンのカートタイヤを使用していたので、ブリヂストンのパフォーマンスをよくわかっていました。当時のDTM(ドイツ・ツーリングカー選手権)で、AMGメルセデス・ベンツのマシンはダンロップタイヤを使っていたのですが、何とか彼らはアドバンテージをとりたいと考えていたわけです。それで、『ブリヂストンがモータースポーツを一生懸命やってるし、一度話をしてみよう』ということになったらしく、そのピアダーデさんがある日東京に来たのです。僕はヨーロッパから帰国した当日だったのですが、ピアダーデさんから『会いたい』という連絡を受けてお会いしました。そうしたら、共通の友人がたくさんいることがわかり、意気投合しまして。何とか一緒にDTMをやりたいね、ということになったのです」と安川が当時を振り返る。
ピアダーデ氏の招きでDTMが行われるホッケンハイムを訪れた安川は、メルセデス・ベンツやBMW、アルファロメオが走り、考えられないほどの観客がひしめく夢のような光景を見た。
「ここにブリヂストンが入ることができれば、素晴らしい結果につながる」との想いを強く抱き帰国する。
すぐさま「これくらいの予算で参戦したい」と経営陣のひとりである小野晃煕専務(当時)に告げると、「そんな予算は会社にはない。半分だったらいい」との返答を受けた。そう言えば安川が諦めると考えたのかも知れない。しかし安川は、「半分でもいいです」とすぐさま返答し、参戦の了承を取り付けてしまったのだ。
「きっと専務はあきれたでしょうね」と、安川。すぐに「予算を半分取ったからやるぞ」と東京・小平の技術センターに告げ、DTM参戦に着手したのだ。
「はじめたらこっちのもの」という読みが安川にはあった。DTMにはそれだけの価値があると直感していたのだ。


1991年、ブリヂストンがサポートしたAMGメルセデス・ベンツのエース、クラウス・ルドウィック選手がDTMのシリーズランキング2位を獲得した。
1992年、
再びミシュランに飲まされた煮え湯
ブリヂストンのDTMでの戦績は「世界にインパクトを与えた」と言うに値するものだった。1991年から1995年までの5年間で、ドライバーズタイトル3回、メーカータイトル4回をAMGメルセデス・ベンツとともに獲得している。タイヤ性能としても、速くて重いDTMマシンの走りを、フォーミュラカーより細いタイヤで支えることは困難な課題であり、ライバルに打ち勝ちながら性能を進化させる開発は、F1をめざすブリヂストンにとって貴重な経験となった。
そして、1992年のニュルブルクリンクのレースで、ミシュランに再び煮え湯を飲まされる経験もした。予想を越える低温のウェットという条件のなか、ミシュランタイヤを装着した4輪駆動のアルファロメオに、1周6~7秒も離されてしまったのだ。ブリヂストンタイヤを装着したAMGメルセデス・ベンツはフロントエンジン・リア駆動と、滑りやすい雨の路面では4輪駆動に対して不利な車両だった。が、大幅な遅れは、タイヤ性能によるところが大きいのは誰の目にも明らかだった。
そのレースからDTMの現場担当となった浜島は、安川とともにAMGメルセデス・ベンツのモーターホームに呼ばれ、首脳陣から叱責を受けた。机を叩いて激怒したマネージャーから、「次の予選はミシュランとピレリを装着する」と言い渡された。
1982年のヨーロッパF2での苦い経験から10年を経て、またもやシーズン途中で他メーカーにスイッチされるという屈辱を味わうこととなったのだ。いずれも相手はミシュランである。スイッチされたのは予選のときだけで、ドライの条件では、AMGメルセデス・ベンツはブリヂストンを装着し、DTM全体で見ればブリヂストンは大きな成功を収めた。しかしこの屈辱は、ブリヂストンのモータースポーツ関係者にとって忘れられない出来事となり、その後さらなる勝利をめざす強力なモチベーション源となるのだった。


1992年、1994年はルドウィック選手、1995年はベルント・シュナイダー選手。ブリヂストンを装着したAMGメルセデス・ベンツチームはDTMでチャンピオンを獲得した。
トラブルに対する
対応力の強化につながった
DTMでの屈辱にブリヂストンの開発陣は打ちのめされたが、すぐに対応し雪辱を果たしたのだ。
ブリヂストンにある技術をあらためてリサーチし直すと、提案されながらも採用していない技術があった。シリカを配合するアイデアである。現在では、ウェットの低温グリップを向上させる常識とも言える技術だが、当時はまだ前例のない技術だった。ブリヂストン社内でも提案されてはいたが、シリカを配合すると製造が難しくなることから今後の検討技術として採用には至っていなかったのだ。
モータースポーツタイヤの開発スタッフは、突貫でシリカを入れたウェットタイヤをつくった。そしてDTMに投入。屈辱のレースから数戦後のウェットレースでAMGメルセデス・ベンツが装着し、見事優勝。雨の中でドライブしたクラウス・ルドウィック選手は、「このタイヤなら4輪駆動はいらない」と豪語し、ブリヂストンスタッフに感動を与えてくれた。

タイヤにとってきわめて過酷なDTMへの参戦によりブリヂストンは、トラブルへ独自の技術で迅速に対応するという高いスキルを身に付けることができた。
素晴らしい
ビジネスツールとなったDTM
「ブリヂストンのタイヤを販売するために、こんな強い武器はない」
ブリヂストンのDTM参戦を、ブリヂストン・ドイツ販売の社長、ウンター・ハウザー氏(当時)が賞賛した。
DTMでタイヤを供給するAMGも協力してくれた。当時、メルセデス・ベンツの購買部門では取引先の数を減らす取り組みをしており、ブリヂストンもことごとく納入を断られる状況にあった。しかし、AMGではブリヂストンタイヤを使い続けてくれたのだ。もちろん競合もあったが、AMGがメルセデス・ベンツの商用車部門などを紹介してくれ、ブリヂストンの直需部門と販売部門の努力によってメルセデス・ベンツでのマーケットシェアが確保されていった。
そのとき、直接世話をしてくれたのが、現副社長のノルベルト・ハウ氏で、その上司がユーゲン・フーバート氏やディーター・ツェッチェ氏など、錚々たる人物だった。
DTMでブリヂストン装着車が勝利を重ね、彼ら首脳陣がブリヂストンを温かい目で見てくれた。そしてこのときの関係が、F1参戦2年目にマクラーレン・メルセデスがブリヂストンタイヤを装着しチャンピオンを獲得するという成果につながるのだ。

苦難も経験するが、DTMでの数多くの勝利は、ブリヂストンの欧州でのブランドイメージを押し上げることとなった。現地のブリヂストン販売店にとってもそれは追い風となった。写真は、1994年にチャンピオンに輝いたAMGメルセデス・ベンツのルドウィック選手。
インディとインディライツに
ファイアストンの資源を集中
ファイアストン買収後、海崎洋一郎社長(当時)が、「ファイアストンはもっと活力を出さないとだめだな」と話した。それで、インディ参戦の話が浮上することになった。
安川は「F1の方が世界的規模でいいのではないか」と、海崎と話し合いを重ねた。副社長であり技術統括の原田も、事あるごとに「F1参戦」を唱えた。ファイアストンはかつて、F1にもインディにも参戦していたことがあったからだ。
しかし、メジャーレースにカムバックするには地元アメリカのトップカテゴリーであるインディからはじめるのが順当だということになった。当時のファイアストンは、小さなモータースポーツカテゴリーを手広くサポートする体制であったが、ブリヂストンがそのままたくさんの小カテゴリーをサポートし続けるにはあまりにも負担が大きいため、すべてのサポートをいったん白紙に戻し、インディとインディライツだけに力を集中させる体制に切り替えたのだ。
1995年、
インディのトップチームへタイヤを供給
インディに参戦する際、モータースポーツ推進室(旧モータースポーツ推進グループ)の安川は、「トップチームとやらないと勝てないだろう」と考えた。
当時、DTMに参戦していたメルセデス・ベンツの知り合いを通じ、インディのトップチームのオーナーであるロジャー・ペンスキー氏を紹介してもらう。そして、ホンダエンジンを搭載してインディに参戦しはじめたチーム、チップ・ガナッシもあったことから、ホンダに対し「ぜひインディでファイアストンのタイヤを使ってください」と依頼した。のちに社長となる技術トップの渡邉惠夫が交渉に臨み、ブリヂストンが技術的支援を行うことを約束し1995年からの参戦が実現した。その後、1996年にファイアストン装着車が早々にチャンピオンを獲得するなど、優れた結果を残せたのはトップチームとともに走り出したからと言えるだろう。


インディへのカムバックにより、ファイアストンブランドへの注目を高めることをめざした。トップチームへの供給が、その後の快進撃につながる。
実際にやってみなければわからない
インディの難しさ
ヨーロッパF2参戦のあと、ル・マンやDTMを経験し、ブリヂストンのモータースポーツ参戦体制は、設備やロジスティック(物流)といったインフラ面がようやく確固としたものになっていった。
しかし、技術面ではチャレンジの連続だった。インディについてもそうである。スポーツプロトタイプカー耐久選手権のマシンであるグループCカーへのタイヤ供給の経験から、400km/hレベルの高速耐久性についてもブリヂストンは自信を持っていた。世界最速といわれるインディも、速度としては同様のレベルである。しかし、最初に持ち込んだ試作タイヤは、トレッドゴムが剥がれるブリスターをあっという間に起こしてしまった。
その理由は、絶えず高速走行を続けるオーバルコースでタイヤに加わる負担は、それまでのサーキットレースに比べて格段に高いこと。そして、ウイングカーであるインディのマシンのダウンフォースがきわめて高く、バンクによって横Gが縦Gに変わることでタイヤにかかる垂直荷重がより大きくなったことだった。
試作タイヤをつくるにあたりそうした情報が明確になっていなかったため、ブリスターを起こしても仕方ない状況だったのだ。アメリカのレースは、そうした情報の集まり方を含めてすべてが未知だった。

インディへの参戦は、きわめて貴重な経験となった。このレースにより、ブリヂストンのタイヤ技術、特に高速耐久性は飛躍的に向上した。
インディはF1につながる
貴重な経験となった
すぐさまブリヂストンは対策を行った。
トレッドコンパウンドの耐熱技術、トレッドコンパウンドと構造の接着技術を格段に向上させ問題を解決したのだ。これは、インディを経験しなければ身につけられない技術だった。そしてもうひとつ、当時のインディにはやがてF1で闘うことになるグッドイヤーも参戦しており、ライバルについて学べたこともインディ参戦のメリットとなった。
ファイアストンの21年目のカムバックとなった1995年のインディでは、ユーザーとなったドライバーはわずか5名だったが、シーズンを通じて2勝を挙げることができた。そして、2つのリーグに分かれた翌1996年は、両リーグでチャンピオンを獲得。ブリヂストンとファイアストンの名を全米にアピールするとともに、F1に臨むブリヂストンにとって重要な追い風となった。

1996年のインディ最終戦、ファイアストンユーザーが表彰台を独占した。参戦2年目のこの活躍は、F1参戦をめざすブリヂストンにとって大きな支えとなった。