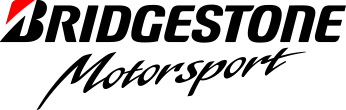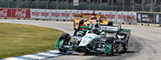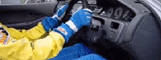ブリヂストンにとって、いよいよ迎えたF1最終年。
前年、望みながら実現できなかったフロントタイヤのサイズ変更を行うなど、
最後まで"よりよいタイヤの追及"を止めようとはしなかったブリヂストン。
そして2010年11月14日アブダビ。F1というモータースポーツの世界最高峰を舞台としたブリヂストンの
14年にも及ぶ長い旅は、ついにゴールを迎える。
最後のシーズン、その序盤に掲げた課題
F1最終年といえども、ブリヂストンのチャレンジング・スピリットには何ら変わりはなかった。「やっておくべきことがありましたから」と浜島は言う。
ひとつは、チームから要求のあった"スペック間のパフォーマンス差が少なすぎる"ということに対する対応だ。2009年、サーキットによってはブリヂストンが持ち込んだ2つのスペックの性能格差が小さく、結果的にレース戦略の幅に広がりが持てないことがあった。この要求に応えることが、2010年用タイヤのスペック決定に際しての基本方針となる。
次に、2009年シーズン開幕前にブリヂストン自身が望みながら叶わなかった、フロントタイヤのサイズ変更である。これについては「狙い通りのバランスとなり、オーバーステアがかなり消えました」と浜島も満足げであった。
さらにもう一つ、2010年からレース中の燃料給油が中止となったことへの対応もあった。前年に比べ、スタート時の車両重量が100kg程度増え、タイヤへの負担が大きくなった。そのためリアタイヤの構造を、より耐久性のあるものに変更しなければならなかったのだ。

シーズン序盤のポイント、
それはトルコGPのターン8
第7戦トルコGP。ここに浜島を始めとするブリヂストン・スタッフの面々は、ある思いを胸に抱きながらやってきた。
「ターン8を克服できるか?」
このコーナーに対する特別な思いは、2007年に遡る。このときレース後半まで3番手を走行していたマクラーレンのハミルトンが、ターン8に進入しようとブレーキングを開始した瞬間、右フロントタイヤのトレッドが突如、剥離してしまったのだ。このときのことを、浜島はよく覚えていた。
「ハミルトン選手のタイヤの使い方が突出していたということもありますが、結果としては我々が用意したタイヤの安全性が足りなかったわけです。以来、このコーナーを克服することはひとつのテーマとなりました」
実際にはトルコGPの舞台となるイスタンブール・パークのターン8は、すでに2008年に克服していた。しかしここがタイヤに厳しいサーキットであることに変わりはない。しかも2010年シーズンは燃料補給の廃止、フロントタイヤの幅狭化とタイヤに厳しい要素が並ぶ。「技術面では興味深いところがありましたが、その一方で現場にいるものとしてはドキドキだったんです」と浜島も白状する。結果としては、まったく問題なくレースを終えることができ、「今シーズンの光明が見えたレース」と評する結果となった。
「タイヤに厳しいサーキットというのは、5つ。トルコ、シルバーストン、スパ、モンツァ、そして鈴鹿です。この5つのサーキットに、どれほど安全性が高く、性能のいいタイヤを投入できるかということが、我々の技術的な課題。そのチャレンジは、ワンメイク供給時代のやりがいとなっていましたね」
たとえシミュレーション技術が進化したとしても、それはあくまで机上のこと。実際のレースでは何が起きるかわからない。それがレースというものだ。だからこそ、タイヤに厳しいサーキットに行くときは、それがたとえ何度目であっても緊張するのだという。そして普段よりも多くのエンジニアをサーキットの現場に動員し、その場ですぐに検証するという作業も行っていた。
例えばベルギーGPの舞台であるスパ-フランコルシャン。ここにはオー・ルージュという、世界に名だたるコーナーがある。ここの垂直荷重は世界一だと浜島は言う。だから、たとえ何回走っても、毎年、違うタイヤを持ち込むのだから不安が消えることはないのだそうだ。"我々は前に進んでいるはずだ。だけど、本当に大丈夫だろうか"。......その心配が決して尽きることがないのが、レースというものなのだろう。


現役唯一の日本人ドライバー、
小林可夢偉のこと
「トヨタF1チームからデビューした2009年シーズンの終わりから見ていて、本当によくやっているな、と感心しています」
浜島がそう語るのは、2010年にザウバーからレギュラードライバーとしてF1デビューを果たした、小林可夢偉のことである。
2010年シーズン序盤、リザルトが残せずに苦しんだ小林。第7戦トルコGPで初ポイントを獲得すると、そこから徐々に安定したレースを見せるようになる。そのことから、"今年一年での成長を感じますか"と問いかけると、浜島はそうではないと答えた。
「F1に来てからというよりも、2009年のGP2で、彼はとても多くのことを学び、成長したと思いますよ。あの年の春、GP2アジアシリーズで小林選手はタイトルを獲得しました。それでちょっと調子に乗ったところがあったかもしれません(笑)。でもその後、舞台をヨーロッパに移して行われたGP2の本シリーズで、ずいぶんと痛い目に会いましたよね。そこでさらにたくさんのことを学んだと思います。それはコース上以外のことも含めて。例えば政治的なことであったり、スポンサーへの接し方であったり。そういった経験を重ねた上でF1に来たのがよかった。その上で、いまは実績を残している。彼の成長を語るとしたら、そこまで遡って考えるべきかもしれないですね」
小林のいいところは、その正直さだと浜島は言う。例えば2010年前半にチームメイトとなった大ベテラン、ペドロ・デ・ラ・ロサに対し、"ドライビングに対する対応力では自分は劣っている。だから(デ・ラ・ロサから)学ばなくちゃいけないんです"ということをコメントしていたりする。これはつまり、人の意見を聞く耳をきちんと持ち、自分のいるポジションを客観的にわかっているということ。「だから成績が残せているんじゃないか」と浜島は見ているそうだ。
もうひとつ披露してくれた、小林についてのエピソード。それはF3時代のチームメイトであり、2009年のF1ワールドチャンピオンとなった、セバスチャン・ベッテルの可夢偉評である。
「"どうして、あのコーナーで可夢偉のほうが速いのか、僕にはわからない。自分にはとても走れないようなスピードで、コーナーをクリアしてくるんだよ、可夢偉は"。ベッテル選手がそう評する速さを、小林選手は持っているんです。がんばってほしいですね」


最後の鈴鹿、
そして忘れられぬ日本のファンのこと
鈴鹿は、母国日本のサーキットであるということ以上に、ブリヂストンにとって特別な意味を持つ場所である。F1タイヤを初めてテストしたのは鈴鹿。F1で初めてのタイトルを獲得したのも鈴鹿。そしてミハエル・シューマッハが久しぶりのタイトルを決めたのも鈴鹿であった。浜島も「非常に思い出の残るサーキット。難しいコースレイアウトのおかげで、我々のタイヤもここまで成長できたんだと思っています」と、その思い入れを語る。
迎えた最後の鈴鹿。グランプリスクエアに用意されたステージでは、連日さまざまなイベントが開催された。もちろん、そこには浜島も加わり、ファンとともに最後の日本GPを楽しんだ。印象的だったのは、雨で予選が中止となった土曜日のイベント。びしょぬれの地面に座り、トークショーを楽しんでくれるファンの姿を見たとき、言い表せないほど感激したと浜島は言う。
「レースの期間中、サーキットホテルに宿泊していました。毎朝、パドックに出勤するわけですが、その間に実に多くの旗を見かけました。"ありがとう"であるとか、"また帰ってきて"であるとか......温かい言葉の数々は、本当に心に沁みています。その気持ちに応えるためにも、F1で培った技術を、市販タイヤやほかのモータースポーツ・カテゴリーに生かしていかなければならないと、いまは強く思っています」
タイヤメーカーを、これほどまでに応援した国は日本だけかもしれない。それは、ブリヂストンがF1に対していかに真摯に接してきたかを、日本のファンが正しく理解していたということの現われではないだろうか。
だからこそ日本のファンはブリヂストンに対して、"ありがとう"という言葉を贈るのだ。


ブリヂストンにとってF1は、
代えがたき学校のようなものだった
80年代初頭、世界のモータースポーツへの挑戦を始めたブリヂストン。そこからル・マン24時間レース、ドイツ・ツーリングカー選手権(DTM)、インディカー・シリーズと、さまざまなカテゴリーを経験しながら、一歩一歩準備を進め、1997年についに念願であったモータースポーツの最高峰F1にたどり着く。そこからの14年間は、息つく暇もないような、熱く激しい戦いの日々だった。その戦いの舞台から、身を引くことになったブリヂストンにとって、F1とはなんだったのか......戦いを終えた今だからこそ、ブリヂストンのF1活動を代表する2人に聞いてみた。
モータースポーツ推進室長として、ブリヂストンのF1活動をマネジメント面から支えた安川ひろしは言う。
「F1は世界のトップが集まる学校でした。我々ブリヂストンは、そこですごく多くのことを学ばせてもらい、そして培ったものはそのまま誇りとなった。F1活動は、計り知れないほど大きな意味を持っていたと感じています」
そしてもう一人、浜島裕英は言う。
「本当に大事なのは、これからです。14年間に及ぶF1活動の中で培ったものをマニュアル化し、それを運用できるようにしておくこと。特に、国内で参戦しているSUPER GTは、今もコンペティションがありますから、F1で蓄えた技術をそこに応用展開することが必要ですね。ただマニュアルとして残すということではなく、実際に使うことでマニュアルの内容が更新され、生き続けていく......それこそが、"技術の継承"にほかならないと思うのです」
F1という、世界最高の舞台に確かな足跡を残したブリヂストン。
その実績は揺るぎなきものとしてF1史に刻印されるとともに、ブリヂストンの技術開発やブランド価値の向上、人材育成といった企業活動の糧となり、次なる一歩へと活かされていくのである。
そして、戦いを見守ってきた人々の心の中に、いつまでも生き続ける事だろう。