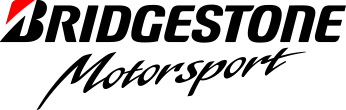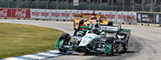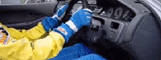ホンダとともにヨーロッパF2に参戦し、世界への扉を開けたブリヂストン。
初年度にチャンピオン装着タイヤとなった翌年、新たに参戦して来たミシュランに
歴然とした差を見せつけられ、挑戦の意欲をさらに高めることとなった。
世界的視野で見ると、
まだ会社の規模が違い過ぎる
その後も、モータースポーツ推進グループとモータースポーツタイヤの開発スタッフは、「F1に参戦したい」という想いを強く抱き続けた。しかし、会社の規模を比べるとブリヂストンは、当時のF1タイヤサプライヤーであり、世界トップ企業のグッドイヤーと比べると大きな隔たりがあった。
「参戦をすぐに決断することはできない」と、会社から正式な返答を得てF1への参戦活動をいったん断念した。とにかく国内レースに専念しようということになり、国内トップカテゴリーのF2において技術を磨き、ライバルタイヤ勢に対しても圧倒的な強さを誇るようになった。
空力マシンの登場で
タイヤにも変革期が訪れる
この頃からフォーミュラカーは空力によるダウンフォースを採り入れるようになっていた。
空気の力でマシンを路面に押し付け、タイヤに掛かる荷重を増やしてグリップ力を高め、コーナリングスピードを上げる新たなマシンの設計思想である。
それはすなわち、タイヤに掛かる負荷が増大することを意味する。それまでのバイアス構造では強さが足りず、摩耗と発熱が課題となり要求されるグリップ力を達成できなくなっていた。また、高速走行時に遠心力によるタイヤの膨張を抑えきれずにサスペンションの動きを変化させるため、空力を考慮したベストセッティングが得られにくくなった。
その頃欧州で先行して開発されていた強靭なベルトを持つラジアル構造にすれば、この課題を解決できるのだ。空力マシンがいち早く登場したF1でレーシングラジアルが装着されると、ブリヂストンも早々にラジアルタイヤ開発に着手した。

日本に入ってきた初のウイングカー、マーチ792を駆る星野一義選手。増大したダウンフォースによってタイヤの剛性アップを図るとともに、サスペンションとのマッチングが重要な課題となった。
1980年、
苦労したレーシングラジアルの開発、世界への扉
将来F1タイヤの開発を率いることになる浜島裕英が、モータースポーツタイヤの開発部署に配属されたのもちょうどこの頃だった。浜島は、実はまったくモータースポーツの経験がない技術者だった。しかし、与えられた条件のなかで勝てるタイヤの開発に打ち込む情熱は尋常ではなかった。
浜島をモータースポーツ開発部に抜擢したのは元副社長で技術統括の原田忠和だった。彼の粘り強い性格を見抜いた原田は、レーシングラジアルタイヤの開発を充実させつつ、F2、F3000などのフォーミュラレース活動を行いながら、内心ではF1進出をめざしていたのだ。
現場では、新たなレーシングラジアルの開発に果敢に挑みながらも、なかなか一筋縄ではいかず苦労していた。1980年秋の日本グランプリで中嶋悟選手のマシンに初投入して手応えを得、1981年から国内F2の全ドライバーのマシンに展開。中嶋選手が81・82年と2年連続チャンピオンになるものの、レーシングラジアルの開発は決して順調ではなかった。実戦での性能が安定せず、それまで勝利を重ねてきたバイアスタイヤにドライバーが慣れていたこともあり、多くのドライバーから不満の声が挙っていたのだ。
新人エンジニアだった浜島は、富士スピードウェイでのレース直前に筑波サーキットに置いてあるバイアスタイヤに戻したいとドライバーに言われ、急いで富士から筑波までタイヤを取りに行ったこともあったという。まだ、高速道路のない時代のできごとである。
その頃、国内自動車メーカーのホンダが、第2期のF1参戦を見据え、1980年からヨーロッパのF2に参戦しはじめた。その海外進出に同行し、ブリヂストンとしても「世界に出る」ための扉を開けたいという話になった。


ブリヂストン装着車が1980年の全日本F2でシリーズトップ3を独占するものの、ラジアルタイヤの開発は実のところ困難をきわめていた。写真は、F2を経て日本人初のF1フル参戦ドライバーになる中嶋 悟選手(1980年)。
1981年、
モータースポーツの聖地欧州へとにかく飛び込んだ
1981年、ブリヂストンはヨーロッパF2に参戦したホンダのマシンへタイヤ供給を開始した。欧州に飛び込んだブリヂストンのスタッフには当初、住むところもなければ、クルマもなかった。
のちにホンダの社長になる川本信彦氏が「よければ使ってくれ」と、モータースポーツ推進グループにホンダUKを紹介してくれたのだ。先陣を切って英国に乗り込んだ安川がヒースロー空港からまっすぐホンダUKを訪ねると、のちにアメリカホンダの社長からホンダの副社長になる雨宮高一社長(当時)が応対した。
安川は、「お前、どうするんだ?」と雨宮氏に言われ、「ちょっと間借りさせてください」と答えた。そうして、ブリヂストンは欧州進出への一歩を踏み出した。
あまり迷惑をかけ続けられないため、ロンドンにあって地の利があるブリヂストンの化工品部門の事務所に転がり込み、デスクをひとつ借りた。当時はそれで十分と言えば十分だった。ただ、住むところはなかったため、ホンダチームのメカニックが住んでいたところに同居させてもらう。クルマは、雨宮氏が「これ、使っていいよ」と、親切なことに一台のホンダ車を貸してくれたのだ。ともに闘うパートナーとしての、ホンダの温かい支援によってブリヂストンの欧州チャレンジは可能となったのだ。


参戦体制の準備もそこそこに乗り込んだヨーロッパF2。しかし、参戦初年度でいきなりの勝利。写真は、ブリヂストンタイヤを装着してチャンピオンを獲得したジェフ・リース選手。
誰がタイヤを組む?
たった2名の欧州遠征
参戦当初は、チームに供給するタイヤをホイールに組み付ける者さえいなかった。
何しろ、日本から遠征したのは、安川と浜島のたった2名しかいなかったからだ。
そのとき安川は、F3に参戦しているアラン・ドッキング氏と知り合い、彼に「タイヤを組むんだったら頼んでやるよ」と紹介されたのがトム・ウォーキンショウ氏だった。彼は、シルバーストーンに「ダンロップ・レーシングタイヤ・サービス(DRT)」という会社を所有しており、報酬をまったく要求せずブリヂストンのタイヤを組んでくれたという。それ以来、安川はトム氏と仲よくなり、1996年のF1タイヤのテストで同氏に協力してもらう縁へとつながるのだ。F1への参戦は、こうした人と人の出会いなしでは語れない。まさに、レースを愛するこころざしを持つ人々の情熱と友情の連鎖の結果といえるだろう。
F1参戦時にサービスを依頼することとなる
ピーターとの出会い
その後安川は、ロン・トーナラック氏と出会った。
同氏は、以前ジャック・ブラバム氏のパートナーだったが、ブラバムのF1チームをバーニー・エクレストン氏に売却後、ラルトチームを運営してF2に参戦していた。最初DRTがタイヤを組んでくれたあとは、彼のところのメカニックがブリヂストンのタイヤを組んでくれたのだ。
そうしてしばらく転戦しているうちに、ブリヂストンはピーター・ジェリンスキー氏と出会う。彼は、イギリスでM&Hというアメリカのタイヤ販売に携わっており、F2などのチームにタイヤを販売していた人物だった。安川がピーター氏に「うちのをやってくれるか?」と話したところ、「やりたい」ということで、イギリスのベーシングストークという場所に小さな倉庫を借りて会社を設立した。そこに電話とFAXを1台ずつ入れて、机と椅子を持って来て欧州でのブリヂストンのレーシングタイヤサービス体制が確立されることになった。
ブリヂストンが1985年にヨーロッパF2の参戦を終えて帰国するとき、ピーター氏にはブリヂストンUKの手伝いを依頼した。その後1991年にDTMに参戦するときに再度タイヤサービスを頼み、F1参戦時も同氏にサービススタッフを率いる要職に就いてもらう長い付き合いになるのだった。

ピーター氏(右から2番目)と出会い、現地でのサポート体制を固めることができた。この初の海外遠征でブリヂストンは、単に技術を向上させただけでなく、欧州のモータースポーツ文化に触れ、将来のF1参戦につながる人脈を築くなど大きな収穫を得た(写真は1985年ブリヂストンカラーのF3000)。
1982年、
欧州で味わった蹉跌
「今思えば、赤子のようでしたね。今だから言えますけど、あのときは相手が何をやっているのか全然わからなかった。『どうやったら、ああいうタイヤがつくれるのかな』と、本当に思いましたから。技術的にはヒヨっ子でした。ラジアルタイヤでもヒヨっ子、組織自体もヒヨっ子。82年にミシュランが出てきたときに、モーターホームは持ってるし、リム組みする人とエンジニアは別だし、びっくりですよね。こっちは、ラルトホンダのトレーラーの下にタイヤ積ませてもらってるくらいですから」
浜島は、笑顔を浮かべながら当時のことを振り返った。しかし、この時ミシュランに負けた悔しさが、その後の浜島の強烈な原動力となるのだ。
1982年から参戦してきたミシュランに敗れた後、1983年もなかなか性能が上がらないことから、ホンダのマシンがシーズンの途中からミシュランを使用するようになった。そしてミシュランは、すぐさま日本で『switch to Michelin』という広告を打った。この悔しさを何と表現すればいいだろうか。このときから、浜島は青と黄色の広告を見ると、アドレナリンが出るようになったという。
予選では速いが、決勝では勝てない。
それが、ヨーロッパF2で2年目を迎えたブリヂストンに突きつけられた現実だった。予選で強いグリップを発揮しても、長い距離を走るレースではミシュランタイヤに比べて明らかにグリップが低くなり勝負にならないのだ。参戦1年目にすんなりチャンピオンを獲れたのは、そのときの相手だったピレリやM&Hには勝てたに過ぎず、まだ上には上があるということだった。
『走行を重ねた時の性能低下を抑制する』という、市販タイヤを含むブリヂストン全タイヤの根幹を成すフィロソフィーは、このヨーロッパF2での蹉跌によって生まれたと言っても過言ではない。

体制だけでなく、
レースに臨む意識が違った
日本でテストを行うと、その結果を東京・小平の技術センターにFAXや直接届けるという形でフィードバックし、レースに持ち込むタイヤのスペックをコントロールすることができた。
しかし欧州では、日本で開発されたタイヤが一方的に送られてくるだけだった。欧州でのデータもフィードバックしてはいるが、それを即座に反映するといった体制はできていなかったからだ。そして、つながりにくい国際電話で、やっとの思いで現場の技術者が日本に結果をフィードバックすると、返ってくるのは「タイヤの性能はいいはずだ。使い方が悪い」という叱責だったという。体制の不備はもちろんだが、国内レースで圧勝していた驕りも少なからずあったのかもしれない。
ブリヂストンは、レース前のフリー走行で2スペックを用意して選択することを行っていたが、サーキットに合わせてスペックを変えるという発想はなかった。『この間よかったからあれを持って行こう』というレベルだったのだ。だから、サーキットの特性に合わないと結果が出ない。それに対し、ミシュランはサーキット毎に3スペックぐらいを用意し、サーキットの特性にあわせた対応を行っていた。
また、「とにかく予選で前に出ろ!」というのが当時タイヤ開発を行っていたブリヂストンの開発スタッフの意識であり、決勝でのグリップの持ちに対する理解も薄く、レースに臨む意識そのもののレベルが異なっていたのだ。ただ、このとき、開発担当課長であった高橋史郎は、欧州での事実を謙虚に受け止め、開発として何をすべきかを理論的に構築し、すぐさま問題解決にあたった。
やがて、予選を捨てタイヤの本来あるべきコンセプトとして、『使いはじめから使い終わりまでの性能落差をなくす』という思想での開発に切り替え、ヨーロッパF2でも撤退前にミシュランに勝つことができた。将来、F1参戦の推進において要となる原田は、欧州での最後の勝利の際、あふれてくる涙を抑えきれなかったという。ライバルであるミシュランに対し、ついに一矢報いた瞬間だった。
レース中の性能落差をなくす考えに切り替えるのに時間がかかったが、この経験は、ブリヂストンにとって貴重なものとなった。

1982年、国内F2ではチャンピオンを獲得するが、ミシュランと闘うことになったヨーロッパF2でブリヂストンは苦い経験をすることとなった。しかし、その経験がのちの勝利へと結びつくのだ。
1984年、
世界一の高速ドラム試験機を導入
この欧州での闘いの経験から、ブリヂストンの技術トップと経営陣は、世界一のドラム試験機の導入を決断する。市販タイヤのPOTENZAでも、ポルシェの標準装着タイヤとして採用されることをめざした高性能タイヤの開発を行っており、高速試験機が必要だったのだ。
POTENZAの開発を率いていたのは、東京・小平にある技術センターの川端操課長(当時)だった。情熱あふれる技術者である川端は、当時フィアンセとのデートの最中でさえ、つい夢中になって喫茶店のコースターにタイヤパタンの絵を描いたり、歩いているとき急に停車中のクルマのタイヤを覗き込むほどタイヤ開発に熱中したという。
そして、カブトガニの腹部の模様からヒントを得て、水を排水しやすい対称性パタンであるユニディレクショナルパタンを開発。また、新幹線のレールには継ぎ目がないことから継ぎ目のないベルトを思いつき、ジョイントレス・キャップ&レイヤーを生みだした。その2つの新技術を投入し、高速試験機とサーキットテストで性能を磨き上げたPOTENZA RE71により、1986年に国内タイヤメーカー初のポルシェ標準装着タイヤの座を獲得。その後、フェラーリにも認められ、ブリヂストンの技術を欧州のエンスージアストに知らしめる快挙を成し遂げた。
このニュースを聞いたブリヂストンのモータースポーツに関係するスタッフは、自分たちもいち早く世界で活躍し、ブリヂストンのビジネスをサポートしたいという情熱がほとばしった。


1986年、ポルシェの承認を得たPOTENZAは、続いて450馬力のモンスターマシン、ポルシェ959の承認を獲得した。「時速320kmで20分以上の連続走行が可能」という過酷な装着条件を、高速耐久性の飛躍的な向上でクリアした。
1985年頃から
F1をめざしたテストに着手していた
1985年当時、国内のトップフォーミュラのリアタイヤは、F1のリアタイヤと比べて、幅が少し広くて径が大きいくらいの違いしかなかった。そこでブリヂストンのモータースポーツタイヤ開発スタッフは、F1タイヤを自主的につくって試していたという。
公然と『F1タイヤ』とは言えないため、『ラジアル・レーシングタイヤの基礎開発』と銘打ち、室内試験機だけのテストを行っていたのだ。
やがて1987年からF1が再び日本で開催されるようになると、モータースポーツタイヤの開発スタッフは、鈴鹿サーキットへ足を運び、ストップウォッチを使って熱心に計測を行った。当時のF3000にくらべてどちらがどう速いのかを計測した区間タイムで比較したのだ。
その結果、ストレートのある区間はF1が速いが、S字~ダンロップコーナーを抜けるところまでの東コースはF3000の方が速いことがわかった。ワンメイクだったグッドイヤーのF1タイヤのグリップレベルをそのタイムから推測し、F1タイヤ開発のデータとして活かした。

1988年、
世界ナンバーワンをめざした拡大戦略
1982年のヨーロッパF2での敗戦を振り返ってみると、やはり「企業力の規模の差がかなり大きい」ことが根本にあるのではないかとの見方が浮上した。
その後、ブリヂストンとしても、海外に出て世界のナンバーワンになるにはどうしたらいいのかを考えたとき、会社の経営として、規模を拡大することが検討された。それが1988年のファイアストン買収へとつながったのだ。
当時、モータースポーツ推進グループの安川は、「ブリヂストンにおけるモータースポーツ活動とは何か?」と自問し続けていた。そのとき、現監査役の石橋寬から「安川君、モータースポーツというのはタイヤを売るためのビジネスツールのひとつだ。そうならなくてはならない」と言われた。それを聞いた安川は、自分の意識を変えなければならないと感じた。ただ、レースに出たいと思うだけではなく、企業としてきちんとした目的を策定しそれを達成する取り組みであることが必要なのだ。
そして、「このままだと井の中の蛙になってしまいます。ぜひもう一度海外にチャレンジする機会をつくっていきたい」ということを石橋に話したところ、「今のブリヂストンでは、すぐに実現できないだろう。長期スパンで考えていこう」ということになった。


1988年の全日本F3000。手前は鈴木亜久里選手。この年F3000チャンピオンとなり、翌1989年にF1へステップアップする。
1989年、
F1参戦を現実的な視野に入れたタイヤ開発に着手
その後1989年には、F1参戦を模索していた無限ホンダ(当時)から極秘テストへの誘いを受け、テスト車にタイヤを供給してサーキットを走ることができた。
経営陣にF1参戦を見送る決断を下されながら、「いつの日か理解を得られる」と希望を捨てず、来るべきF1進出のため80年代後半から若い技術者にF1用タイヤの基礎開発を行わせ、無限ホンダとの極秘テストへの参加を推したのは、何を隠そう技術統括の原田だった。
はじめブリヂストンは、ハイパワーのターボエンジンを搭載して高速で駆け抜けるグループCカーのタイヤ技術を流用したテストタイヤで入力データを採り、安全に走れるF1タイヤとしての耐久性を確保する開発から着手した。マシンは、F3000のレイナードのシャシーに無限ホンダのF1エンジンを搭載したものだった。
その年は、国内トップフォーミュラのF3000で星野選手がやっとシリーズ3位になる状況であり、ブリヂストンは国内F3000用タイヤの基礎技術を徹底的に見直す必要に迫られていた。そこで、先進技術を用いた素材の研究やシミュレーション技術を導入し、より良く接地して高いグリップを発揮するには、構造とコンパウンドのトータルバランスが重要であることを見いだした。
その開発思想は、当然ながらF1のテストタイヤにもフィードバックされた。1990年以降は、無限ホンダのテスト車もティレルのF1シャシーとなり、本格的なものとなった。結局テストは1994年まで継続され、開発スタッフから原田へ提出された報告書には、『技術的には2年の猶予があればF1へ参戦できる』と記されていた。しかし、ブリヂストンにはまだF1参戦の計画はなかった。