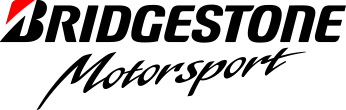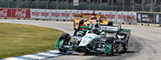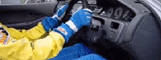1963年の第1回日本グランプリから30年以上のときを重ね
ブリヂストンは、ようやくF1フル参戦のスタートラインに立つことができた。
それは、ブリヂストンの企業力が世界最高峰のレースに挑む域に達した証でもある。
世界一をめざすためには
欧州でも認められなければならない
アメリカにもいいブランドは存在する。しかし、長い歴史を持ち、故に各分野で一流ブランドを生み出した欧州で評価されることは、ブリヂストンというブランドにとってとても重要である。
ブリヂストンが世界ナンバーワンになるためには、欧州での知名度を確固たるものにしなければならない。幅広く知られることも重要だが、そのビジネスに関わりのある方々に愛されるブランドになる必要がある。それには、タイヤをクルマに供給するという実態のあるプロモーション活動でなければ価値がない。
ポルシェやフェラーリの標準装着タイヤとして、ブリヂストンは国内メーカーではじめて採用されるという快挙を成し遂げていたが、知名度としてはまだ十分とはいえなかった。技術力をアピールするとともに、知名度を高め定着させるには、F1は大きなツールになるとブリヂストンのモータースポーツに関わる者は意を決しはじめていた。しかし、経営陣にとってF1参戦のコストは膨大であり、すぐにうなずけるものではなかった。

インディで得たものは多かった。しかし、世界で認められるには、もはやF1は必要不可欠のビジネスツールになるだろうとブリヂストンのモータースポーツ関係者は感じていた。
1996年、
いよいよF1参戦が役員会で決定される
「ブリヂストンが世界一のステージに上るためには、ビジネスツールとしてF1は重要となるだろう」という石橋の言葉を、安川をはじめとするモータースポーツ推進室のスタッフ、原田をはじめとする技術スタッフは信念を持って信じていた。
かつてのように、『レースに出たい』という想いだけではなく、ブリヂストンの名が世界に出ること、ブリヂストンが持っている技術を世界の人に高く評価してもらうことをF1参戦の目的として位置づけていた。
「やはり、自動車メーカーやお客様に評価してもらわなかったら、何ごともはじまらないんです。お客様がタイヤを購入されるのは、クルマを検査に出して『タイヤが減ってますよ』と言われたときです。そして、たいていは『同じのにしてくれ』とおっしゃるか、『安いのを』とおっしゃるかのいずれかです。履き替えの市場でビジネスをしていくには、ハイパフォーマンスを誇るか、現在では優れた環境性能など、技術力を強くアピールしなくてはなりません。そのためには、技術力を訴求するとともにステータスを築くことができるF1が最適であることを強く推しました」と安川は語った。
無限ホンダとの極秘テストで手ごたえをつかんでいた原田は、海崎に「ヨーロッパでのシェアを伸ばすためにはF1参戦しかない」と説得。「失敗したら、クビだぞ」と言われながらも、海崎本人からついにF1進出へのゴーサインを取り付けることに成功する。
そして原田の説得で意を決した海崎は、1996年の2月の取締役員会で「F1に参戦させてください」と大勢の役員の前で頭を下げたという。膨大な費用がかかるF1参戦に対し、当然ながら反対する意見もあったからだ。意を決した海崎は、トップ自ら頭を下げる情熱を示し、2年後の1998年からのF1参戦を決定させたのだ。
かつて、1976年と1977年に富士スピードウェイで開催されたF1へタイヤを供給したあと、「F1に参戦したい」というモータースポーツ関連スタッフの申し出に対し、「参戦をすぐに決断することはできない」と会社が正式な決定を下したのは、当時のF1タイヤサプライヤーで世界トップ企業のグッドイヤーに対し、企業力の点でブリヂストンは大きな隔たりがあったからだ。
また、ヨーロッパF2参戦後の1980年代後半、モータースポーツ推進室の安川が「このままだと井の中の蛙になってしまいます。ぜひもう一度海外にチャレンジする機会をつくっていきたい」という胸の内を石橋に話したところ、「今のブリヂストンでは、すぐに実現できないだろう。長期スパンで考えていこう」という返事が返ってきたのも、ブリヂストンの企業力がまだF1に参戦できるレベルになかったのが主な理由である。
そして今回、F1参戦を決定した前年の1995年、ブリヂストンは売上高を躍進させ、世界で19%のシェアを獲得し文字通り世界一のタイヤメーカーになっていたのだ。ようやく夢のF1に参戦できたのは、そうした企業力の底上げがあってこそだった。
つまり、ブリヂストンのF1参戦決定の背景には、全社員の努力によって、グローバル規模で企業力を向上できたという『あと押し』が基盤にあったことは、明白な事実なのである。

ブリヂストンのF1参戦を決断した海崎社長(当時)。写真は、参戦を果たした1997年の日本グランプリ前に開かれたプレスカンファレンスでの挨拶の様子。
1996年、実際のF1マシンで
貴重なタイヤテストが実施できた背景
「ブリヂストンはいつかF1をやらなくちゃだめだよ」と言ってくれていたのが、エンジン供給でF1に参戦した無限ホンダのトップだった。彼らの協力と原田の決意のもと、1989年からテスト車や参戦を終えたF1マシンでの継続的なテストが行うことができたのはすでにご紹介した通りだ。そしてブリヂストンの参戦が決定した1996年。
「現役のF1マシンで何とかタイヤテストを行いたい」という開発スタッフの声を受けた安川は、ヨーロッパF2参戦時にタイヤサービスをお願いしてから友人として長く付き合っていたトム・ウォーキンショウ氏に協力を依頼した。
アロウズを率いF1に参戦中だった彼は、「グッドイヤーとの契約があるけど、彼らに事情を話してテストしてあげるよ」と言ってくれたのだ。
グッドイヤーが出した条件は、「レースタイヤは供給を続ける。が、グッドイヤーとのテストを今後放棄するなら、ブリヂストンとテストをやってもいい」というものだった。この条件を交わして合意したトム氏もグッドイヤーも懐が深いといえよう。ブリヂストンのスタッフは、グッドイヤーの寛容に感謝しながらトム氏のチームとのテストを開始した。ドライバーには、1996年のF1ワールドチャンピオン、デイモン・ヒル選手も名を連ねた。これも、トム氏の計らいだった。

アロウズのマシンを使い、前年のワールドチャンピオンであるデイモン・ヒル選手がステアリングを握って行われたブリヂストンのF1タイヤテスト。ヒル選手からは「アンダーが出にくく、グリップレベルが高い。周回を重ねてもタイムが落ちにくい」との好インプレッションが得られた。
テストで確かな
手応えをつかむ
現役のF1マシンでのテストは、ブリヂストンのF1チャレンジに光を与えるものとなった。
ライバルのグッドイヤーが1社提供(ワンメイク)でF1に参戦し、タイヤ性能を競う相手がいない状況だったこともあるが、ブリヂストンのF1タイヤを装着したマシンはグッドイヤー同等以上のタイムを示したのだ。
インディの経験から、グッドイヤーのタイヤ開発への対応スピードはそれほど早くないことが推測された。『すぐにでも参戦できるのでは?』という空気がブリヂストンに流れた。

参戦直前の1996年、日本とヨーロッパのサーキットで約8,000kmにもおよぶテストを重ね、ブリヂストンのスタッフは確かな手応えを得ていた。
ライバルを圧倒するために
参戦時期を早めたい
F1参戦が決定した1996年当時、タイヤを開発する東京・小平の技術センターのスタッフは、技術的に万全を期すためにも1998年からの参戦を想定した。
一方、モータースポーツ推進室では、1998年からの参戦となると、1997年の1年間、ライバルに時間を与えることになると懸念していた。1996年からはじめていたテストでは、当時ワンメイクだったグッドイヤーと比較し、ブリヂストンのF1タイヤはいいパフォーマンスを示している。だからこそ、これ以上ライバルに時間を与えたら、相手も開発を進めてしまう。そうなると、参戦初年度でブリヂストンのタイヤ性能に注目を集めることが難しくなり、トップチームに供給するチャンスを減らすことにつながるのではと考えたのだ。
「こういう大きなプロジェクトは世の中の動向や景気で簡単に変更する可能性があるため、少しでも早く参戦発表を済ませておきたい」と考えていた原田は、モータースポーツ推進室の提案も考慮し1997年からの参戦にゴーサインを出した。
原田のこの決断がのちのさらなる成功につながる。参戦初年度の1997年開幕戦で、オリビエ・パニス選手がいきなり5位入賞。続く2年目、グッドイヤーがその年限りでのF1撤退を表明していた1998年には、早くもチャンピオンにまで登り詰めるのである。
もちろん現場では、1年前倒しの参戦の決断に大いに慌てることになった。供給するチームが少ないとはいえ、ほぼ隔週間隔の連戦となるF1に、すぐに安定してタイヤを供給できるかということが懸念されたからだ。しかし、レーシングタイヤの製造を担当する東京・小平の東京工場が、全製造部門からエキスパートを招集し、特別体制で製造にあたる手配をしてくれたことで乗り切る見通しが立った。こうして1996年の夏に、当初の予定から1年も前倒しとなる1997年からのF1参戦が現実として動き出した。

1996年10月9日、東京・京橋のブリヂストン本社ロビーにて1997年からF1に参戦することを発表。タイヤテストへの協力を惜しまず、ブリヂストンユーザーとなるアロウズF1チームのトム・ウォーキンショウ氏と原田がこのときがっちりと握手を交わした。
F1参戦は
ステップ・バイ・ステップで
日本企業は当時、資金にものを言わせていろいろなものを買うといった批判を受けたことがあった。
安川らモータースポーツ推進室のスタッフは、そうした批判につながるようなことはしたくないと考えていた。また、あまり背伸びしすぎて、資金面で着いていけなくなっては元も子もない。彼らとしては、『ステップ・バイ・ステップ』でF1参戦を推進したいとの方針を出していた。
その背景には、人の問題もあった。はじめから複数のチームやトップチームと組んでもマンパワーが追いつかず、生産もロジスティックスも付いていけなくなることが想像できたからだ。そこで、あまり大きくなく、ブリヂストンに好意を持ってくれている5つのチームと契約。しかし、チーム側の都合で1チームが不参加となり実際には4チームでブリヂストンのF1参戦がスタートすることになった。その4チームとは、トム氏率いるアロウズ、アラン・プロスト氏が率いるプロストGP、ジャッキー・スチュワート氏が率いるスチュワート・フォード、それにミナルディである。

参戦初年度にブリヂストンのマークを付けて決勝のグリッドに並んだのは、新しいタイヤで上位進出を狙う4チーム8台となった。写真は、ミナルディの片山右京選手。
1996年の夏、
翌年の参戦に向けてスタート
ブリヂストンのF1レースがスタートするといっても、基地となるところがなければはじめられない。それと、人がいなければ。
開発の方は浜島と同じ技術センターの生方透らが中心となって体制を整えていたが、あとは実際のF1タイヤ供給のマネジメントを、海外の前線基地で実践部隊として中心となる人物が必要だった。
ちょうどその頃、ブリヂストン・ベルギーの駐在を終え日本に帰国しようとしている人物がいた、堀尾直孝である。モータースポーツは未経験だったが、欧州の事情に詳しく語学が堪能で、推進力がある。そして、学生時代に強豪のラグビー部でレギュラーとして活躍した経験から不屈の精神に定評があり、時間のないなかF1参戦の実務を強力に推進するために欠かせないスピリットを持った適任者だった。
再びロンドンの
化工品部門のオフィスを間借り
最初はオフィスも足場となる場所さえなかった。そこで、1981年のヨーロッパF2参戦のときにもオフィスを貸してくれた英国にあるブリヂストンの化工品部門に依頼したところ再度協力を快諾。80年代のF2では机1つ借りるだけで十分だったが、F1に進出する今回は、ロンドン事務所の会議室を1つ貸してもらった。
「これからF1をやるには大きなスペースが必要。とにかく場所づくりからだ」ということで、堀尾が中心になって場所の確保に奔走した。このとき設立に携わったのがブリヂストンモータースポーツUKである。
何もかもがはじめてのことばかりだった。不動産の契約、会社の立ち上げ、人の雇用...。しかし、1997年の開幕までわずか半年しか時間はなく、とにかく急がなければならない。堀尾は、不動産会社から提案されていた4~5箇所の物件候補の絞り込みをはじめた。
ヒースロー空港から近くであること、そしてタイヤを保管する大きな倉庫があり、必要十分な事務所、トランスポーターを何台も置く駐車場を確保できる広さがなければならない。また、F1という世界最高峰のレースに携わるのだから、きれいで洗練された施設であることが必要だと堀尾は考えていた。
候補に挙っていたのは、ヒースロー周辺のいわゆる倉庫街でそのなかから条件に合う場所を見つけ出した。ハイウィッカムという街だった。近くに、小さいが雰囲気のいい街があり住むにも適している。堀尾は、すぐにその候補地を抑え、自分が住む場所も確保した。それまで、ベルギーでタイヤの商品企画とマーケティングに携わり、欧州の事情に詳しい堀尾だったが、さすがに不動産契約ははじめての経験だった。いろいろと勉強を重ねながら、慎重に契約を進めていった。
次に行ったのは堀尾直属の部下となるスタッフの雇用である。
人材派遣会社にコントタクトし、まず信頼できる経理担当を選んだ。偶然にもファイアストンに勤めていた経験があり、タイヤにも詳しい経理のプロと巡り会うことができた。そして、タイヤをホイールに組み付けたり、運搬を行うタイヤサービスは、80年代のF2のときに手伝ってもらったピーター・ジェリンスキー氏が快く引き受けてくれた。人とのつながりの大切さを感じながらのスタートとなった。
その他に、約20名の現地スタッフを雇う必要があり、何人も面接を行った。しかし、堀尾は人材を選ぶプロではない。そこで、化工品部門の山本浩介社長(当時)に面接に同席してもらい、いろいろとアドバイスをしてもらった。
堀尾が選びたかったのは、長く務めてくれるまじめな人物だった。出入りの多い業界ではあるが、長く務めてもらいさまざまなノウハウを蓄積できる人が欲しい。F1チームのような給料は払えないが、仮にどこかに転職したとしても『ブリヂストンはいい職場だった』と言ってもらえる職場にしたいと考えていた。
「お金はたくさん払えないけど、その代りハートフルな職場に務められる」と面接に来た者たちに語った。イギリスは、ビジネスにおいてお金ももちろん大切だが、モチベーションも大切にする国であることを堀尾は長年の駐在経験から学んでいたのだ。
実際、仕事がスタートしてからは勤続5年と10年を迎えた者を表彰した。5年のときは、カルティエの万年筆に表彰者のイニシャルを彫り込みプレゼントした。
また、年末には家族を伴ってのクリスマスパーティを恒例の行事とした。1年のうち多くの日を家族と離れて過ごすため、家族やガールフレンドも同行してのパーティにしたのだ。そして、全員分の宿泊施設を用意する配慮も欠かさなかった。そうして温かく接したこともあり、5年10年在籍する者もおり、ブリヂストンMSUKをあとにするスタッフは少なかったという。

欧州でのモータースポーツの拠点となるブリヂストンモータースポーツUK。ロンドンから20分の位置にあるハイウィッカムに、開幕直前、1997年の1月に稼働しはじめた。

1997年の最終戦、ヨーロッパGPにて。一年間F1で闘い続け、確かな手ごたえを得たブリヂストンのスタッフとドライバーたち。ひとつの仕事をやり遂げた自信とホッとしたような笑顔が見える。