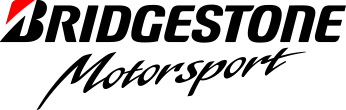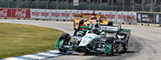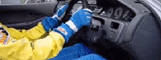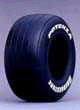|
まずそれまでのスリックタイヤと比較してマイナス面が洗い出された。テストでは、フロントタイヤの摩耗が激しく、極端なアンダーステアが出てしまった。溝が付けられたことによってタイヤ前後輪の摩擦量の比率が大きく変化してしまい、ハンドリングに影響を及ぼしてしまうことが判った。それをどううまくバランスさせるか、さらに、フロントの摩耗をどう低減するかなど様々な課題があった。
これに対応して考案されたのが、フロントタイヤの大径化及び幅広化だった。これでアンダーステアと前後バランスは改良された。初期問題を解決した後に行われたテストではドライバーからコントロール性能はきわめて安定しているという評価を得た。そして12月頃からは次の段階として全体的な性能向上を狙ったテストをスタートしている。
しかし、マクラーレンのデザイナー、エイドリアン・ニューウェイは、この大径、幅広フロントタイヤに真っ向から反対。空気抵抗の増大を嫌ってサイズを小さくするように言ってきたのだ。
テストが進行していくと予測通りにラップタイムはスリックタイヤに比べ3~4秒遅くなっていた。しかし、マシンの幅が狭いことから空気抵抗が減り直線のスピードは変わらなかった。タイヤはかなりのまとまりを見せ、次にタイムアップを図れるスペックの開発を進めた。そしてシーズン開幕を迎えるにあたって耐久性とグリップ性能が高いポジションでバランスしたタイヤを供給できたのだった。
1998年モデルのマシンでスリックタイヤと溝付きタイヤの両方をテストし、双方同等のタイムがマークされたことと、初戦のオーストラリアでポール・トゥ・ウィンを飾ったことでニューウェイもこの大径、幅広フロントタイヤに反対はしなくなった。実際、オーストラリアでブリヂストンユーザーは、ドライバーの意志通りのハンドリングを示したが、グッドイヤーユーザーは苦しいドライビングを強いられていた。
|
|
しかし、グッドイヤーも第3戦アルゼンチンから大径、幅広フロントタイヤを投入、シーズン中盤から終盤にかけては両タイヤメーカーの技術力が真っ向からぶつかり合うこととなった。ブリヂストンはシーズン半ばから3回のスペック変更を実施。小平の工場は休日も返上してF1タイヤの生産を行った。
そしてライバルのグッドイヤーが1998年いっぱいでF1へのタイヤ供給の中止を発表していた。他のタイヤメーカーが名乗りを上げていない以上、1999年はブリヂストンが単独でタイヤを供給、サポートすることとなるのは明らかだった。ライバルがあってこその闘いである。この年に勝つことこそ、大きな意味があった。参戦してわずか2シーズン目でスタッフに与えられた使命はあまりにも大きかったかもしれない。しかし、厳しい闘いの末、母国の鈴鹿サーキットでチャンピオン決定の瞬間を迎え、勝者となった。日本国内で培ったレーシングタイヤのノウハウを世界の場、F1で開花させ勝ち取ったチャンピオンだった。
1998年、新たに導入されたレギュレーションは、タイヤにとっても過酷な状況を生み出すこととなり、それがレースの展開の変化をも生むこととなった。タイヤを使う各チームの戦略、レースマネージメントがレースの面白みを増大させた。つまり、タイヤがレースを変えることとなったのだ。約20年間使用されてきたスリックタイヤの使用禁止は、F1レースにとって大きな出来事であった。タイヤがF1で大きなファクターを占めていることが再認識されたシーズンでもあった。
1999年からは、再び新たな挑戦が待ち受けている。これからは、ブリヂストンがF1を支えて行くこととなるのだ。
|