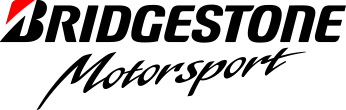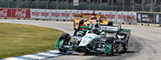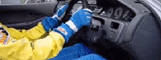|
|
|||||
|
戦から8ヶ月、母国日本で栄光の瞬間を迎えて、プレッシャーから解き放たれた彼らの表情はとても穏やかだった。その目から流れる涙を拭おうともせずにセレモニーを見続ける彼ら、その笑顔と潤んだ目が過酷なシーズンを闘い抜いた勝者の肖像だった。 参戦をさかのぼる8年前に |
サポートしたものだった。その2年間では、バイアス構造のタイヤを開発して供給、 1976年の雨の中で注目されるパフォーマンスを発揮するなど、それなりの成果はあ った。 しかし、無限からの誘いを受けて開発を開始したのは、全く新たなラジアル構造 のF1タイヤだった。まず、最初に無限のエンジンテストを滞りなくサポートするこ とを重視し、壊れないタイヤ作りから入っていった。当時最も耐久性の高かったグ ループCカー用のタイヤ技術を流用したタイヤを製作、F1ではタイヤにどのくらい 縦入力と横入力がかかるのか、などのデータ採りから始め、F1での耐久性を確保し ながら徐々に構造とグリップレベルを変えていった。耐久性を重視した特性から F2、F3000に近いグリップレベル、機敏性を持たせるものへ変更していったのである 。パウロ・バリラ選手がステアリングを握って行われたこの1989年のテストは、 600キロを走り終えている。 1990年以降も鈴鹿における無限との共同テストは引き続き行われ、シャシーもレ イナードからティレルのF1シャシーとなり、より本格的なものとなっていった。一 方、1989年の全日本F3000選手権でブリヂストンはサポートチームのチャンピオン獲 得に貢献できなかったばかりか、サポートしている星野一義選手がやっとシリーズ 3位に入る状況でライバルメーカー、ダンロップの後塵を拝したシーズンであった。 この状況から小平技術センター内のモータースポー |
||||
|
BRIDGESTONE MOTORSPORT |
|||||